- Home
- ようこそ、雀荘「ゴールデンタイム」へ!
- 第十一話「麻雀強かなれど、酒弱し」
第十一話「麻雀強かなれど、酒弱し」
- 2017/11/29
- ようこそ、雀荘「ゴールデンタイム」へ!
- 小説, 雀荘
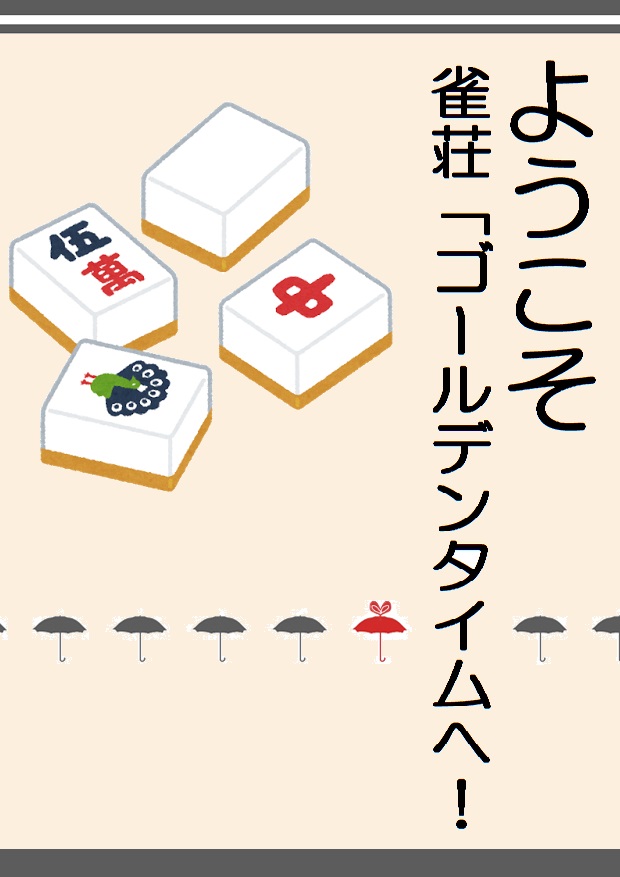
第十一話「麻雀強かなれど、酒弱し」
次局以降、あかねも入るかと誘われたが、首を横に振って辞退した。
ましろと、プロと同卓してみたい気持ちはあるが、
それ以上に、彼女の闘牌を、砂被りの特等席でもっと見てみたいと思ったのだ。
勤務時間ではないから、ひたすら麻雀を見ることに集中できる。
ましろのツモる所作ひとつから、点棒を払う仕草まで、見落としのないように。
結果、四半荘打って、ましろの成績は1-3-2-1の+160.3。
文句なしのトータルトップである。
けれど成績以上に、打牌選択以上に、あかねが目を奪われたのは彼女の落ち着き払った挙措であった。
点棒を授受や副露の際にもほとんど音を立てず、かといって、動作ひとつひとつが遅い訳でもない。
速い、のではなく、早い。そして適切なのだ。
フリー客のように慌ただしいそれではなく、丁寧で、洗練された動きに、あかねは目が釘付けになった。
そしてなにより、
「いかがでしたか?」
振り向いて、微笑むましろに、頷いて応える。
その自信に満ち満ちた表情が、あかねの胸を打った。
麻雀プロという団体や組織の存在は以前から知っていた。
詳しいことは知らなかったが、あるいは、知らないかったからこそ、低く見積もっていた節さえあった。
アマチュアの方が、よっぽど強いんじゃないだろうか、と。
が、その認識は違った。実際的な強さでは、あるいはフリーに足繁く通うアマチュアも、彼らに敵うべくあるのかもしれない。
が、そこには、ましろのように磨き抜かれた麻雀はきっとないだろう。
「やっぱりましろさんはつえーっすわ。敵わねぇ」
「四半荘だけですから、運が良かっただけですよ」
「むしろ短い本数で負けたから、よけい悔しいんっすよー」
東出の言うこともさもありなん。少ない半荘数の方が、当然運の介在する余地は大きい。
十本、二十本と続ければ続けるほど、実力差というのは、僅かに、しかし如実に表れるものだ。
「さて、ましろはこの後どうする。なんだったら、フリー打っていってくれてもいいけど」
時計を見れば、時刻は午後六時半。そろそろセット客が増え、フリーも経ち始める時間帯である。
「今日は、非公式での里帰りみたいなものですから、また後日改めて参ります。その時は、きちんと城崎として」
立ち上がって、帰り支度を始めるましろ。荷物を受け取ったところで、
「ところであおいさん、あかねさん。この後はお暇ですか?
よろしかったら、お食事などいかがでしょう」
「行きます!」
(今日から)憧れの城崎プロからの食事のお誘い。これを、断れるようなあかねではないし、そもそも、今日の予定は何もない。
家に帰ったところで、ひとりで外食する気もないので、冷凍ご飯と昨日の残り物で済ますことだろう。
身を乗り出して即答するあかねだが、その隣で、口元を引きつらせて玉虫色の表情をするあおいには、まだ気づいていない。
丸川の焼肉屋はこの時間にはまだ暖簾を出していない、ということで、近くに居酒屋に来た三人。
ちなみに、東出も同行とする主張したが、十九時からの出勤であったので、当然不可。
さんざん駄々をこねたが、最後には筒井に耳を引っ張られて、奥へと引っ込んでいってしまった。
鼻歌交じりにスキップさえ踏みそうなあかねとは対照的に、あおいは浮かない面持ちである。
あかねがその事実にようやく気付いたのは、ましろがゴールデンタイムに顔を出した後には必ず来るという居酒屋の前であった。
「あの……その、もしかしてあおいさん、怒ってます……?」
おずおずと尋ねるあかねは、以前、あおいに連れられた丸川の焼肉屋で女子大生らしからぬ(あるいは、女子大生だからこそ?)醜態を晒し、
挙句、目が覚めるまでの面倒をあおいに看てもらうという前科を思い出した。
あおいは、あるいはそれを咎めて眉をひそめているのかもしれない。
「え、なんで?」
「だってその、このあいだ私、あおいさんにずいぶんご迷惑を掛けたのに、性懲りもなく……」
「そんなこと。そんなの、キャバクラで働いてたらいつものことよ。でも、飲みすぎには注意するのよ」
「はぁい。でも、あおいさんがあんまり乗り気じゃなさそうだから……」
「それはね――」
あおいが語り始めようとした瞬間、ましろががらりと引き戸を開いて、ふたりを中へ入るように促す。
「予約していた城崎と申します」
ましろの準備抜かりなく、個室座敷を事前に予約していた様子。
それを見て、あおいがひとつ、深々とため息を吐いた。
「あかねさん、あおいさん、今日は日本プロ麻雀連合の城崎ましろではなく、
ゴールデンタイムの先輩のましろとして、接してください。遠慮無用です」
つまり、今日は彼女のおごりだということ。あかねは目を輝かせた。
ましろに誘われてのことだったが、一応自分の飲み食いした分くらいは支払うつもりでいたのだが、一気に肩の荷が下りる。
(違う違う。飲みすぎるなって、さっきあおいさんにも言われたばっかりだった!)
以前は、ビール五杯目までの記憶しかない。ということは、それ以上は禁物、ということ。
心のノートにビールは五杯まで、と書き連ねておく。
それぞれの注文が決まったところで、チャイムを鳴らす。はーいという女性店員の声。あれ、どこかで。
「おまっせしましたー」
関西訛りの口調。マニッシュショートの髪型は、
「南条!」
「あれ、中井ちゃんやん」
あかねの大学の同輩、南条その人であった。
はじめは不意の遭遇に驚いていた南条だが、あかね以外の人間を見つけるや否や、
いつもの乱暴な言葉遣いとは打って変わって、丁寧な自己紹介。ちょっと意外である。
「あの……失礼やとは思いますけど、もしかして、城崎プロですか?」
「はい。日本プロ麻雀連合に所属しております、城崎ましろと申します」
とたん、南条はぱっと顔を明るくして、
「お会いできて光栄です! うち、ファンなんです! よかったら、サインとか……」
「お見知りおきいただきありがとうございます。ですが、今日はプライベートですので……」
しゅんと項垂れる南条。喜怒哀楽の激しい彼女を見るのは、それなりの付き合いであるあかねも初めてのことで、ちょっと面白い。
「ゴールデンタイムというお店で、近々予定がありますので、その時にいらっしゃっていただければ、ぜひ」
「ありがとうございます!」
ふだんは硬派ぶっているのに、存外にミーハーな南条を驚きと共に見つめていると、案の定ジト目で以て睨み返される。
が、注文を聞き取ると、意外にも何も言わずにそのまま退出してしまった。
あとで、いまのバイト先の先輩だと連絡しておいてあげよう。
「あかねさんはふだんからお酒をよく飲まれるんですか?」
「いえ、お金ないので……。それに弱いみたいですし。でも、お酒はおいしいと思います」
「私とおなじですね。私も、あんまり強くないんですが、好きなんです」
うふふと笑うましろは、やはり美人だ。
こんな人がお酒を飲んだら、色白の肌にぽっと朱が差して、きっと絵になるに違いない。
到着するビール、ハイボール、焼酎ソーダ割り。それぞれ手にとって、いざや乾杯。
ビールをごくり。ああ、うまい。麦の香りと炭酸の爽快感が鼻腔を潜り抜けていく。
それから、ビールの後味残る口内に、塩味の効いた枝豆をぱくり! 至高の瞬間である。
第一印象はとっつき辛そうに思えたましろも、
酒を酌み交わし話をしてみれば、あかねやあおいに比して口数は少ないものの、不愛想という訳ではない。
麻雀の話、プロという団体の話、ゴールデンタイムの話……職場、趣味を同じうする三人の話は尽きることを知らない。
しかし、相も変わらず、あおいは不安げな表情を取り崩さない。
店の前ではああ言ってくれたものの、依然私の飲酒量を憂いているのだろうか。
実際、ビールは三杯目に差し掛かっている。
というのも、酒好きを自称していただけあって、ましろの飲むペースが早く、
――一杯目のジョッキを空にする頃には、二杯目のグラスワインを飲み干さんとしていた――
またあおいも、仕事柄か、彼女に負けず劣らず、それに引っ張られるように、あかねの手もついついビールに向かってしまっているのだ。
ほっけの身をついばみながら、あおいを盗み見る。
「どうしたの?」
「お酒、そろそろ飲まない方がいいのかなぁ、って……」
あおいは、煙草のフィルターをトントンとテーブルで叩きながら、
「もう、気にしなくていいって言ったのに」
そして、火を点けて、
「あかねちゃんなんて、まだまだ序の口よ」
顎をしゃくって指す先には、
「ましろさん!」
頬どころか、耳、首筋、胸元まで真っ赤にしたましろが、座った目でおちょこを傾けるましろがいたのだった。
一目で、彼女が酔っ払っていることがわかる。尋常の様子ではない。
けれど、徳利から独酌する手は止まらない。
「あかねさぁん」声の調子も、どこか間延びしている。「お兄様は、お宅ではどのような方だったんですかぁ?」
その酔いどれた姿態に、あかねが目が点になった。
あおいは、やれやれとばかりに煙草の煙を天井に吐いている。
呆然と座り尽くすあかねであったが、何度もしつこく名前を呼ばれて、ようやくあの城崎プロとましろ酔っ払いが同一人物であることを認識する。
「兄貴は、そりゃもう勝手気ままなやつでしたよ。
急にふらっといなくなったと思ったら、二週間後にハワイ行ってきたって言って、マカデミアナッツ持ってきたり……
しかも、その旅費、勝手に私のお小遣いも使ってたんですよ!」
兄とのエピソードを思い出すだけで、苦虫を千匹嚙み潰したような顔をするあかねだが、ましろは意にも介さず、
「うふふ。自由な方だったんですねぇ」
なんて、見当はずれのことを言うもんだから、あかねもどっちらけだ。
「あおいさん……」
助けを求める目、
「まぁ、こういうことよ」
は、紫煙の彼方にかき消えた。
「あかねさぁん」へべれけましろの管巻きは続く。「お兄様は、――」
その先は、もごもごと料理を頬張りながら喋るものだから、聞き取れなかった。
が、あかねは妙な引っかかりを感じた。
まさか。そんなことは。
と思いながらも、一度疑問に思ったことは明らかにしなければ気が済まない性質のあかねは、
まるで、あなたはサンタクロースを信じていますかとでも尋ねるような気分で、
「ましろさん、もしかして、兄貴狙い……なんですか?」
一瞬の、否、長い長い沈黙。
さっきまでうるさかった居酒屋の喧噪が遠く聞こえる。
あおいは、煙草に火を点けて、二度、三度、中空に煙を吐き出す。
ビールジョッキに出来ていた結露の雫が、ゆっくりと重力に従って、テーブルに落ちた。
その時、ましろは、さっきまでの酔人然はきれいさっぱり消え去って、あたかも、恥じらう少女のように(!)はにかんだ。
「ありえな――――――――――――い!」
狭い個室の中を、あかねの怒号が鳴り響いた。
その大音声たるや、あおいが煙草を取り落すほど。
「ない、ない! それだけは! 絶対にやめておいた方がいいですって!」
「あかねちゃん、声大きすぎ」
「す、すいません――じゃなくって、あのアホ兄貴だけは、ダメです!
若い身空で、人生棒に振る気なんですか!?」
あかねは、実兄中井はじめの悪辣さを、身に染みて知っている。
プロ団体内や電波放映上での外面をどう取り繕っているのかは知る由もないが、
少なくとも、その内面の壮絶さたるやを、あかねは知っているのだ。
「若いだなんて。あかねさんに比べたら、私なんて、もうおばさんですよぉ」
「ましろさんいくつなんですか?」
「今年で三十三です。あかねさんの、ちょうど一回り年上になりますねぇ」
「えっ、兄貴よりも年上!?」
ちなみに、はじめとあかねは十違いである。
「お兄様は、年上はお嫌いなのでしょうか……。
この頃は、若い女流の子たちと、よくテレビに出ているのをお見掛けしますけれど……」
一転、テーブルに突っ伏して沈み込む。たしかに、これは面倒くさい。手に余る。
「と、ともかく、兄貴はやめときましょう? ほら、他にも素敵な男の人はいますから」
「……先ほどから、お兄様はよせ、よせ、と仰られていますが、あかねさんは、その、もしかして、世にいう『ブラコン』という方なのですか?」
あかねの脳内で、何か、かろうじてつなぎ止まっていたものが、ぷつんと音を立てて切れた。残っているビールを一気に飲み干して、吼えた。
「そんな訳あるか――――――――――――!」







