- Home
- ようこそ、雀荘「ゴールデンタイム」へ!, 連載麻雀小説
- 第十四話「オカルトって信じますか?①」
第十四話「オカルトって信じますか?①」
- 2017/12/14
- ようこそ、雀荘「ゴールデンタイム」へ!, 連載麻雀小説
- 小説, 雀荘, 麻雀
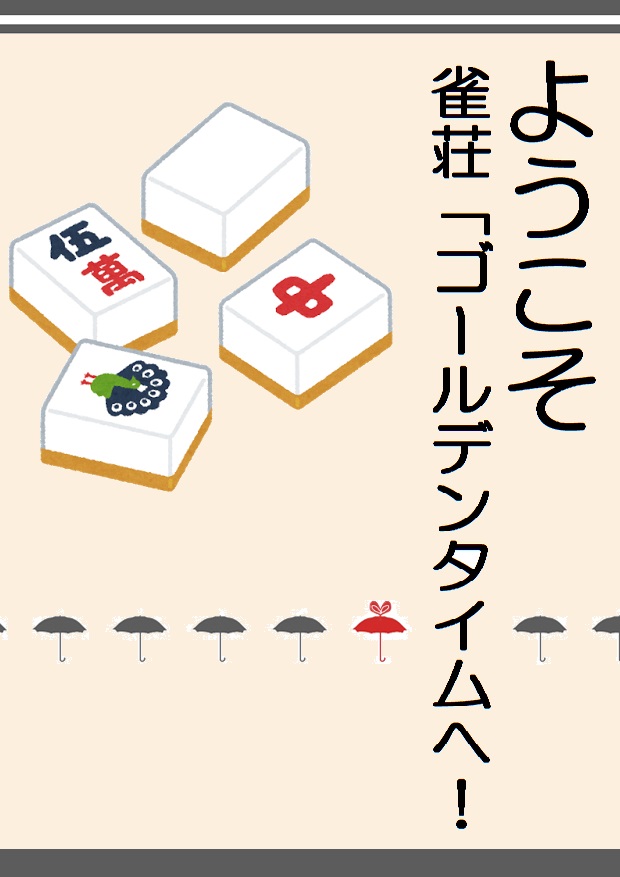
第十三話「オカルトって信じますか?①」
ましろの言葉に、あかねはちょっとへどもどして、唸りつつも、首を横に振る。
「それって、流れ論、的なやつですよね」
麻雀とオカルトは、切っても切り離せない関係にあるといっても過言ではない。
麻雀に限らず、運の要素の割合が大きい場合、その運の部分に重きを置く人がいるのも、致し方ないことと言える。
あかね自身は、彼女が言ったようにそういうものは一切信じていない。
というのも、そんなことを言い出せば、牌効率などの麻雀理論のすべてが瓦解してしまうと、考えている。
仮に、三面張リーチに対して、カンチャンリーチで立ち向かわれて、一発で放銃してしまっても、
確率的にはありうることだから仕方ない、と割り切ることにしている。
「いまのは、純粋なオカルトという訳ではないんですけどね」
東出たちはすぐに次の局を始めているので、ちょっと距離を取る。
「あかねさんなら、あそこでペンチーソウ聴牌でリーチしていましたか?」
「そうですね……。たぶん、ヤミテンにはしていないと思います」
「たぶん、私もプロの公式対局ではそうしていると思います。
東出さんも、メンバーとして本走している時は、そう取っているでしょう」
ましろの含みを持たせた言い分を、あかねはいまひとつ理解が追い付かない。
「あまりきれいな打ち方ではないということです。
例えば、昨日の私の白単騎もそうですしね。
三面張リーチに対して、単騎待ちで追いかけられ、あまつさえ、和了られたら、むっとするでしょう?」
なるほど。間違いない。いかに低確率とて、可能性がある以上は押し黙るほかないのだが、頭には来る。
「真似しちゃだめですよ?」
「したくてもできないですよ。
だって、そもそも、山に8索が生きてるとも思わなかったですし……」
「あら、そんなことありませんよ?」
ましろはいたずらっぽく、不敵に微笑んで見せる。
またしても、あかねにはなんのことやら。
「あかねさんだって、例えば、7索がぜんぶ見えていて、
おまけに9索までぜんぶ場に出ていれば、山に8索があるのでは、と思いませんか?」
「まぁ、そんな極端な場況でしたら、たぶんそう思いますけど……」
「いまのあかねさんには、河と自分の手牌くらいしか見えていないかもしれませんけど、
実際はもっとたくさん情報があって、対局者の理牌の癖、切り出し位置、視線の動き、打牌のリズム……
慣れてくると、そのあたりのことも、自然と目に入ってくるんです。
必ず、萬子、筒子、索子、字牌という風に理牌する人の右三から、9索が出てきたら、端の二枚は字牌対子と思いませんか?」
たしかに。他家の手が短くなって4センチになった時なんかは、
最後の切り出しから待ちの色を想像したりもする。
「ほかにも、リーチ者の和了以外でのツモ牌に対する反応もありますし、上家の打牌に対する反応ですとか……
けれど、いまのあかねさんは、気にしない方がいいと思います」
ましろが思いのほかそっけない物言いをするものだから、眉をひそめる。
言う通り、麻雀の腕はまだまだ未熟だが、そこまで直截に言われると、あかねのちっぽけなプライドに障るというものだ。
けれど、ましろも、その様子をいちいち見抜き去って、慰めるように、あるいは元気づけるように、
「少なくともいまは、です。
相手のことよりも、まずは自分のことを盤石に。
よほどの相手でない限り、あかねさんがミスなく打ち続ければ、向こうから崩れてくれるはずですから」
と言うが、あかねはどうにも釈然としない。唇を尖らせて、不平アピール。
「盤上を見渡すのは、手牌を見ずともミスなく打てるようになってからですよ。
オカルトを信じるのも、それからで構いません」
「別にオカルトを信じるつもりはないですけど……」
「でも、たまに思いませんか?
オりてるつもりの字牌対子落としで放銃したりすると、嫌な予感がするでしょう?」
「まぁ、しますね」
「それをあかねさんご自身が思わなくっても、そんな風に対局者が思ってくれるだけでも、有利になることが多いんです。
『嫌な打ち込みをした。しばらくは手が冷え込みそうだ』なんて風に相手が委縮して、牌効率を最大化しなかったり、もしくは、リーチに対して臆病になったり」
あかねは、かつて東出に言われた言葉を思い出していた。
麻雀は人の打つゲーム。いくらデジタルだのオカルトだの持ち上げても、結局は毎回の牌選択は人間が行っているのだから、
緩手もあれば反対に確率を超えた一手も存在するのだと。
「これは私の持論なんですけれど、『対局者の頭を揺さぶる和了』というのが、麻雀には存在するんです。
ほら、格闘技なんかでもよくあるでしょう?
生憎ながら、私は造詣が深くないのですが、絶対に放銃することないと思って自信満々で切った牌が、
七対子に刺さって、その上裏まで乗って跳満放銃、挙句箱割れまでしたら、しばらく立ち直れそうにないでしょう?」
そんなこと、想像するだに恐ろしい。
が、あかねもまた経験のない訳ではない。
親の先制リーチに対して、二萬の四枚壁の向こう側、河に一枚、自分が二枚持ってる一萬を対子落としして、
一発で打ち込み、顔を青くした覚えがある。
「狙ってまでする必要はないのですが、そういうことがあった後、多くの人はミスをします。
意識的無意識的であれ、前に出すぎたり、逆に退きすぎたり……ともかく、自ら崩れていくんです。
そんな中、どんなことがあっても常にいつもと同じ調子で打ち続けられる、というだけでも、難しいことなんです」
自分の過去の麻雀を思い返してみて、心当たりがあってはっとする。
オカルトを信じていないようにしているつもりでも、あるいは、信じないようにと意固地になっているが故に、
ものの見事に正常な思考を崩してしまったことも、ままあった。
子の跳満に放銃した後、大物手の成就ばかりを夢見て、
3900の鉄板チーテンを取らずに門前に固執してしまったことも、一度や二度ではない。
麻雀はメンタル。かつての東出の言葉が改めて、すとんと腑に落ちたような気がした。
「私でも、役あり両面をあえて取らずに、役なしシャンポンでリーチすることもあります。
けれどこれは、『ツいていないから』ではなく、『山になさそう』だから、するんです」
はっきりと言い切ったましろの顔に、いつもの妖精めいた可愛げはなく、
凛然と、年月に裏打ちされた不撓の清々しいまでの矜持だけが伺える。
その様に、あかねは、ただただ見惚れてしまっていた。
「……私の顔に、なにか付いてますか?」
照れくさそうに頬をかきかき、ましろがけろっといつも可憐ぶりを取り戻して微笑む。
よく見ると、いつもは雪のような肌が少し紅潮している。こほん、こほんと咳払い。
「ところで、そういう戦略的なことは置いておいて、ましろさんはオカルト信じる人なんですか?」
素朴な質問に対して、ましろはちょっと考えるような素振りをして、
「そうですね。かなり信じる方だと思います」
という回答に続いて、
「先日の白単騎も、その最たるものですね。
それまでずっとひっかけ含みの9筒単騎でヤミテンしていたんですが、白をツモってきた時に、なんとなく、ピンと来たんです」
言いながら、曖昧にはにかむ。
先ほどまで、大上段からあかねに牌効率を大切に、普通に打てと高説のたまいながら、
いざ突っ込まれた時には、打牌の不合理さにバツが悪い。
「ゴールデンタイムですと、筒井さんが一番のオカルト派ですね。
効率的には全く意味のないチーもしますし、暗刻の役牌をポンしたり……
それから、役なし門前を大明槓して、しかも新ドラまで乗せて、嶺上開花だけで和了したりだとか……」
「す、すごいですね……」
「ふだんお店で本走する時はしないのですけれど、
ご友人とスリーやファイブでセットを打つのを何度か見学させて頂いている時には、見たことがあります。
オカルト派、と言っても、基礎の理屈を蔑ろにしているという訳ではなく、
ここぞという急所で、そういう風になさるみたいです」
ちなみに、スリーやファイブというのはレートの呼称だということを、あかねはつい最近知った。
千点=百円のことをピンというのに対して、ゴールデンタイムのような低レートの千点=五十円をハーフ、二百円ならリャンピンもしくはツーという。
スリーなら三百円、ファイブなら五百円という具合である。
筒井の打ち筋以上に、そのようなレートの麻雀が、漫画の世界ではなく本当に行われていることの方が気にかかる。
あかねなんぞ、千点=五十円のレートでひいこら言っているのに、ファイブとなればその十倍である。
一度箱割れすれば、たやすく三万円からの支払いである。
話に一区切りがついた時、ちょうど東出からラストの声が掛かった。トップは僅差で東出であった。







