- Home
- ようこそ、雀荘「ゴールデンタイム」へ!
- 第八話「印象操作」
第八話「印象操作」
- 2017/9/27
- ようこそ、雀荘「ゴールデンタイム」へ!
- 三麻, 小説
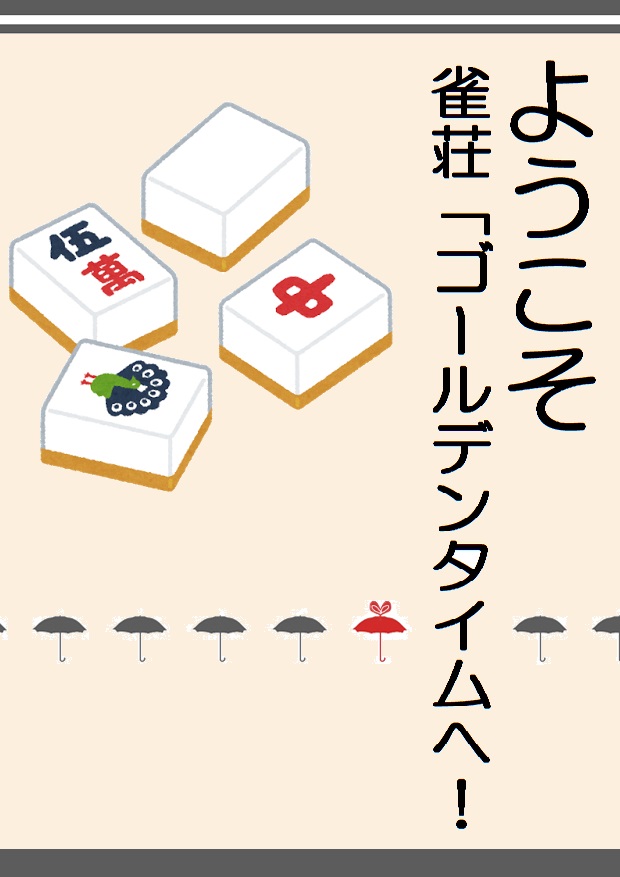
「第八話 印象操作」
翌朝、あかねが目を醒ました時、背中の慣れない感触に思わず身じろぎした。
体を起き上がらせようとしたところで、まるで熱を出した時みたいに全身が気だるい。
しかも、頭痛まである。
もしかして風邪をひいてしまったのだろうか。
この時期はクーラーの冷気に当たって体調を崩しやすいものだが、これではバイトに支障が出てしまう。
重たい瞼をこじ開けて、そしてそこで気が付いた。自分の家ではない。
(あれ、昨日なにしてたっけ。ていうか、ここって)
目の前に広がるのは、知らない真っ白な天井だった。
ここはどこ。なぜ、どうして、私はここで横になっているのか。
思い出そうとするが、頭の痛みがひどくて、たまらず呻いた。
「あかねちゃん、起きた?」
「あおい、さん」
喉を震わせる自分の声が、あまりにも掠れていて我ながら驚く。
それに、口の中が気持ち悪い。歯磨きをせずに眠った翌朝よりも、ひどい味がする。
「あはは、すごい声。昨日のこと、覚えてる?」
「昨日、……」
ゴールデンタイムを上がって、あおいに焼肉をごちそうになり、それから、それから、……。
タンの分厚さに驚いたことは覚えている。ロースの柔らかさも覚えている。四杯目、五杯目のビールジョッキを空にしたことも。
けれど、自分がどうして知らないソファで横になっているかは、さっぱり思い出せない。となれば、結論はひとつ。
「私、酔いつぶれちゃってました?」
「それなりにね」
「す、すみませんっ」
お酒を飲む、ということもまたずいぶん久しぶりのことだったから、加減を仕損じて、すっかり酔いつぶれてしまったということを自覚し、顔から火を噴きそうなくらいに赤面して、穴があったら入りたい、とはこのことだ。
「ここって、あおいさんのおうちですか?」
「そう。ゴールデンタイムから電車で一駅のところだから、あかねちゃんの家からもそんなに遠くないと思うわ」
失礼と思いながらも、あかねは好奇心抑えきれず、あおいの部屋の中をぐるりと見回した。
小物や家具の類は少なく、すっきりしている。インテリアといえば、机の上に小さなサボテンの鉢植えが置かれてあるくらい。
服やアクセサリが乱雑に散らかっているあかねの部屋とは大違いである。
「あんまり見られると、さすがに照れるんだけど……」
「すみません。でも、なんだかあんまり生活感ないなぁ、って」
「まぁ、あんまり家で何かする、ってこともないからね。お風呂入って着替えて、寝るくらいだもの」
「そんなものですか」
「そんなものよ。キャバクラと雀荘、夜の仕事掛け持ちしてると、どうしても、ね」
少なくとも同じ大学生の下宿先は、あかねの部屋のように散らかっていることが多かったし、小奇麗に掃除していても、部屋の隅には空の酒瓶が転がっていたり、実家から持ってきた大量の荷物に埋め尽くされたりしていることが多かったから、なんとも納得しがたい。
「あかねちゃん、今日出勤でしょ? そろそろ帰って身支度した方がいいんじゃない?」
「えっと、いま何時ですか?」
あおいの差し出したる時計盤の示す時刻を見て、あかねはぞっとした。
自分は、いったい何十時間眠りこけていたのか。いくら日曜日とはいえ、いくら酔いつぶれたといえ、寝すぎにもほどがあるというものではないか。
出勤まで、焦るほどではないが、今から家に帰って、お風呂に入って準備をしていたら、時間なんてまたたく間に過ぎていく。
「お暇します! 焼肉、ごちそうさまでした! 送ってくれて、しかもソファまで貸していただいて、ありがとうございました!」
「気を付けてね。駅は、マンション出て、右に曲がってまっすぐ行ったところ」
玄関まであおいに見送ってもらって、急ぎ足で駅へ向かう。
帰り際に、もう一度ぺこりとお辞儀をする。
明るいところで見たあおいの顔は、少し疲れていて、余計に申し訳ない気持ちになる。
今度はこっちからなにかごちそうしよう。そのためには、もっと麻雀の負けを減らして、給料を増やさなければ。
胸に、新たな決意を秘めつつ、あかね帰宅。
さっとシャワーを浴び、夕飯を食べようとして、しかし材料がないことに気付いて、諦めた。
昨日のロースの味を思い出して空腹感を紛らわせようとしたが、一層腹が減るばかり。
ベランダに干しっぱなしの洗濯ものから適当に着替えを見繕う。が、ひと揃えの靴下がどうしても見つからない。
部屋の中も探しても、やはり見つからない。洗濯機の中には、いくつもあるというのに!
面倒だからって洗濯を後回し後回しにしていたツケを後悔しながら、結局色の良く似た別々の靴下を履いて、あかねを家を飛び出した。
ドタバタしたため、予定よりも時間がない。
立川ビルの前にたどり着いた時、なんとか十五分前で、あかねは深呼吸を二度三度、気分を落ち着ける。
正直、頭はまだ痛い。おまけに体もだるい。なんなら、ベッドに入ってまだまだ眠っていたい。
が、顔を両手でパンパン、自分に気合を入れる。まずは大きな声であいさつだ。
「おはようございまーす!」
出勤時のあかねの威勢の良いあいさつも、今ではゴールデンタイム名物のようなものだ。
待ってましたと言わんばかりに、おはようと返してくれる客もいるくらいだ。
「あ、東出さん、おはようございます」
休憩中なのか、ソファでくつろいでいる東出を見つけて、彼にも大きな声であいさつ。
「おはよう中井ちゃん。……どうしたの、調子悪そうだね」
あかねの気丈な空元気をいち早く、めざとく見つけ出した東出は、首を傾げながら、頭のてっぺんからつま先まで彼女を睥睨する。
「靴下を右左間違えて履くと、力が出ない人?」
「靴下は関係ないです!」
しかも、靴下の柄違いまで見抜かれてしまったもんだから、恥ずかしいったらない。
「実は昨日、というか今日、かくかくしかじかで……」
事のあらましをかいつまんで説明する。そういう訳だから、靴下のことも仕方ない、と締めくくるが、それはものぐさなだけと返されて、返す言葉もない。
「丸川さんとこ行ったんだ。あそこ、うまいよなぁ。けど、ビールだけでつぶれるって、何杯飲んだんだ?」
けらけらと小馬鹿にするように笑う。東出は、笑うと、ただでさえ細い目がさらに線のようになる。
なにか、思い出せそうな気がして、しかしすぐに頭がずきりと痛んで諦めた。
「東出さんも、行ったことあるんですか?」
「うん、何回かね」
言いながら、東出がポケットから取り出した煙草のパッケージに、あかねは見覚えがあった。
煙草を吸わないあかねにとって、知っている銘柄は店で置いてあるものだけで、東出のそれは、そのどれとも違う。
だのに、なぜか見覚えがある。
「東出さん、それ、何かで有名な煙草だったりします?」
「別にそんなことないよ。なに、煙草吸いたいの?」
「そういう訳じゃないんですけど……なんか、見覚えがあって」
東出は目を細めた。そして口の中で煙をためると、勢いよくあかねに吐き出した。
「わっ、なにするんですか!」
「オコチャマにはまだ早いね」
「もう二十歳超えてます!」
「酒飲んで酔いつぶれて記憶トンでるようじゃ、まだまだ」
「じゃあ、大人は酔いつぶれても憶えてるっていうんですか!」
あかねの反駁に、東出は動きを止めた。煙草の煙が、ゆらゆら立ち上る。
「大人はねぇ、忘れたくっても忘れられないもんだよ」
なんて意味深なことを言うもんだから、二の句が継げず、押し黙った。
ふだんは軽薄な、ひょうきんな東出の、いつになく真剣な――本走中ですら、見たことがないほどに――表情を、
あかねは今まで見たことなかった。
「ちょっと煙草買ってくるね。すぐそこのコンビニ」
そしてごまかすように、逃げるように、エレベーターに乗り込んでいってしまって、やきもきする。やるかたない。
ちょうど入れ違うタイミングで、再びエレベーターが昇ってきて、あかねは頭を切り替える。
「いらっしゃいませ! って、丸川さん」
「おう、あかねちゃん。昨日は大変だったな」
現れたのは、まさに話題にのぼっていた焼肉屋店主丸川で、改めて会うと、ちょっとした威圧感がある。
きっと、あおいに紹介されていなければ、一生関わり合うことのなかったような人だろう。
そう思うと、なんだかちょっと嬉しくなる。
「打てる?」
「大丈夫です! えっと……」
新たに来店したお客をフリーに案内する時には、いくつか決まりごとがある。
ひとつは当然、メンバーの本走している卓であること。
もしもフリーが丸で回っている時は、メンバーを入れてツーメンで立てるか、もしくは、卓割りを再編する必要がある。
そしてもうひとつは、適当な状況であるか。
「適当」の定義は店によってまちまちだが、
例えば、南二局のようにスタートからずいぶん進行してしまった局面からお客に入ってもらう訳にもいかないし、
東二局といえど、点棒状況が大きく崩れた場面では、他の同卓者から不平が出かねない。
それから、他家のリーチが掛かっているような状況も望ましくない。これは言わずもがなである。
「東二局親番、24000点持。先制リーチ打ってます」
「ああ、じゃあそこ入るわ」
ちなみに、こういう時に、今まで本走していたメンバーはやりきれない。
せっかくの親番で先制リーチを仕掛けられたのに、お客様優先で交代しなければならないのだから。
あかねも何度か経験しているが、理不尽すら感じる。
丸川の麻雀を打つ手つきは、その節くれだった指先とは裏腹に、丁寧できれいだ。いかにも打ちなれている。
「あかねちゃん、結構負けてるんだってな」
「はい……」
うしろで見惚れていたあかねに話しかけながらも、その動作によどみはない。
滑らかに壁牌まで腕が伸びて、盲牌だけで判断して、ツモ切る。
「おっと、ツモ、4000オール。悪いね、譲ってもらって」
先ほどまで入っていたメンバーは苦笑いするほかない。
「俺の麻雀でよかったら見てきな。そこまで、達者なものではないけどよ」
後ろからの立ち見を、特に、じっと観察されることを気にするお客は多い。
ある程度仲の良くなった人ならばともかく、向こうからそう言ってくれるのはありがたい。
それから三時間、ドリンクの注文や卓掃の合間合間に、丸川の麻雀を見続けた。
彼の麻雀は、端的に言って、力強かった。
子のリーチ程度なら、リャンシャンテンの形からでも押し返し、追っかけリーチをかぶせ、そして見事に打ちとってみせたり。
時には、二枚切れのカンチャンでも聴牌即リーを敢行、結果、後筋ひっかけの形になって、出和了したり。
いまの自分には真似のできない打ち方であった。が、引き出しひとつ増えたような気がする。
休憩に入って、あかねは、丸川の麻雀の疑問点をノートにまとめていた。
タイミングがあったら聞いてみよう。そう思った矢先、
「あかねちゃん、休憩中だったか?」
「はい。丸川さん、もう終わったんですか?」
「これから店の仕込みだからな」
「ちょっとお時間もらえたりしませんか?」
言って、ノートにまとめた疑問や自分の考えとは違うところを質問していく。
丸川も悪い気はしないようで、逐一、優しく応対してくれる。
「あと、ここのダマテンなんですけど。巡目も浅いし、待ちも良いし、私だったらリーチしてると思うんですけど……」
「おお、あれか。あれは、一種の『印象操作』みたいなもんだな」
耳慣れない単語が飛び出してきて、思わず困惑顔になる。
「まあちょっとした小細工だな。例えば、ある人がやたらと筋ひっかけしてくるとして、
そういう人のリーチ宣言牌が、四萬だったり、五筒だったりしたら、ちょっとその筋を切りにくいだろう?」
なるほど。それで、印象操作、という訳か。とはいえ、いまの例えでは、あかねの疑問点とはあまり結びつかず、腑に落ちない。
「前局にヤミで満貫、跳満を和了った後に、先制リーチを打たれたりすると、ちょっと怖いだろう? もしかすると、今回も手が入ってるんじゃないか、高いんじゃないか、って風に」
「な、なるほど……」
「麻雀ってのは人がするゲームだからな、印象ってのは案外大切なんだ。
この人のリーチは怖い、とか思わせられたなら儲けモンだ。それだけで、リーチに対して、強く来られなくなったりするからな。
よく『流れ』っていうのをみんな言うが、相手に『流れがある』って思ってもらえるだけで、ずいぶん楽に麻雀が打てる」
東出が言っていた、「メンタル」とはまた違った麻雀の部分。
あかねもまた、知らず知らずの内に意識していたはずである。
この人は強いから、きっと好形のリーチを打ってきているはずだ――蓋を開けて見れば、ただのカンウーピンなんてこともままあった。
麻雀の強さと待ちは関係がないはずなのに!
「おっと、そろそろ行かないと。また店の方にも来てくれよ」
「はい! ありがとうございました!」
麻雀を上手く打とうとしすぎている。
あおいの言葉が、すこし分かったような気がした、あかねであった。







