- Home
- ようこそ、雀荘「ゴールデンタイム」へ!
- 第六話「初野あおいという人①」
第六話「初野あおいという人①」
- 2017/8/30
- ようこそ、雀荘「ゴールデンタイム」へ!
- 三麻, 小説
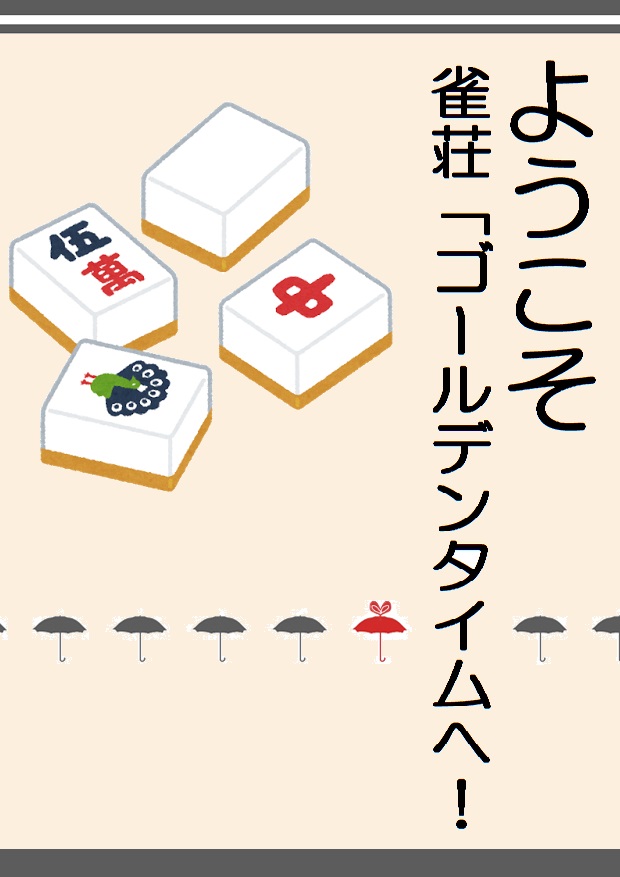
「第六話 初野あおいという人①」
「という訳で、終わったらごはんいきましょう」
突然、夕食の誘いを受けて、あかねは当惑した。
今日も今日とて、あかねは――幸運なことに?――立ち番にかかりっきりで、
給料損失の憂き目に遭うことなく、
にわかに忙しくなり始めたゴールデンタイムのフロアで、卓掃に勤しんでいた。
そんな折に、以前と同じように、シフトでもないのにひょっこりと現れたあおいが、
不意にそんなことを言い出すものだから、さもありなん。
今日のあおいは、サロペット、スニーカー、後ろ向きキャップに胸元にはサングラスと、
全身マニッシュで、前回の少女っぽさはどこへやら。
「その、お誘いは嬉しいんですけど……」
とはいえ、あかねにも事情というものがある。
むろん、その事情というのは「懐」事情にほかならない。
昼飯をコーヒー一杯すすって空腹に喘いでいるような女子大生が、
そうやすやすと外食に行けるべくもない。
「もちろん。おごりに決まってるじゃない。
後輩に出させる先輩なんて、先輩じゃないもの」
胸を反らして意気揚々とするその財源は、ちなみに筒井出資である。
「あおいさん……好き!」
飢えた女子大生は施しに弱い。
あわやあおいに抱きつきそうになるのを何とか堪えて、
振り返って時計を見ると、午前一時、残り二時間。
なんだか、無性にお腹が減ってきたような気がする。
「それじゃまたあとで来るから。ちゃんと働くのよ?」
「はい!」
ふんすと鼻息荒く、勤務後のお楽しみを心の支えにあかねは一層やる気をみなぎらせる。
手を振ってエレベーターに乗り込むあおいを見送って、
ふと、あかねは不思議なことに気が付いた。
こんな時刻から、あおいはいったいどこへ行くというのだろうか。
そもそもこんな時間までなにをしていたのだろうか。
女性のひとり歩きに危うい時間帯である。
(改めて考えてみると、ふだんのみんなってどうしてるんだろう)
ゴールデンタイムが現在抱えるアルバイトの人数は十五人。
中には、週末一日しかシフトに入っていない人や、
東出のように週五、六で出勤している人もいる。
ちなみにあかねは週三日、あおいもまた同様である。
東出は、自分自身で一人暮らしのフリーターと言っていた。
休みの日にはパチンコに行くか、彼女とデートしているのだそうだ。
さて、あおいはいったいメンバー業の他に何をしているのだろう。
少なくとも、この仕事だけでは、週三シフトでは食っていけないはずだ(たとえ一カ月のトータル成績がプラスでも)。
あかねこそ、仕送りとして家賃光熱費の類を両親に負担してもらっているから、
辛うじて雨風をしのげているものの、
それがなければ今頃、公園で新聞紙にくるまっていてもおかしくない。
「あかねちゃーん、ラスト―」
「はーい。すぐ行きまーす」
にわかにフロアが忙しくなってきて、あかねは思考を切った。残り二時間、笑顔で乗り切ろう。
「おつかれさまでーす」
午前三時きっかりにあかねがゴールデンタイムを後にすると、
ちょうどエレベーターを降りたところであおいと鉢合わせた。
店を出る直前まで、東出が本走中ながらも恨めしそうな視線をあかねに向けていたが、
その意図に気付くべくもなく、さらりとエレベーターに乗り込んだ。
午前三時の街角は、街自体が眠りに落ちているみたいに静かで、人の気配はほとんどない。
時々遠くの幹線道路の方から車のエンジン音が聞こえてくるばかり。
空を見上げれば、夏の地平線はそろそろ白みはじめ、神秘的でさえある。
「おつかれ、あかねちゃん。行こっか」
いつものごとく駐輪場に自転車を取りに行こうとしたところで、
あおいにそれを制止せられ、手招きされるままについていくと、車が一台。
「あおいさん、運転できるんですか?」
「そりゃあね。実家が田舎の方だから、車ないと不便だしね」
さっそうと運転席に乗り込むあおいは、いかにも格好いいお姉さんだ。
胸元のサングラスもよく映える。
「あかねちゃんは免許持ってないの?」
「大学に入ったら取ろうと思ってたんですけど、なかなか忙しくって……」
授業と授業の合間に時間を見つけては麻雀を打ち、
アルバイトのない日は集まって麻雀を打っていたあかねは、
確かに、多忙な大学生活であったに違いない。
ほとんど無人の街中を快速で進んでいく車は、
どんどんあかねの生活圏内から離れていく。
自転車での移動を主とするあかねにとって、
車で十分の距離は、すでにちょっとした冒険だ。
「こんな時間に開いてるお店ってあるんですか?」
「車で二十分くらい走ったところにね、焼肉屋があるのよ。焼肉は嫌い?」
「大好きです!」
牛肉なんてぜいたく品、まさか口にできる日が来るなんて!
焼肉、という言葉を聞いただけで、あかねの口の中はよだれまみれ。
ともすれば、じゅるりと音すら聞こえそうだ。
「焼肉なんてもう二度と食べれないかと思ってました……」
「大袈裟すぎよ。
あかねちゃんも、もうちょっとフリーに慣れれば、すぐに成績もついてくるわ」
「……私、麻雀下手なんでしょうか」
あかねの不安げな問いに、あおいは即答しない。唇を二度、三度震わせて、それから、
「下手じゃないわ」
あおいの答えに、あかねはほっと胸を撫でおろしかける。
「けど」
続く言葉に、身を強張らせた。
「上手に打とうとしすぎてる、っていうのかな」
一瞬、あおいの言葉の意味が分からなかった。
負けないためには上手に麻雀を打とうとするのは当然のことで、
給料が出ないと嘆いている状況で、誰か下手を打とうものか。
困惑顔のあかねをちらと見て、あおいはすました顔のまま、続ける。
「例えば、自分が子で、場に一枚切れのカンリャンピンで聴牌して、先制リーチもなし。
他に聴牌気配もない状況で、あかねちゃんならどうする?」
「たぶん、スーピン引いて両面になるまで待つか、
ほかのところで両面作れるんだったら、カンチャン搭子を落としていくと思います」
「私だったら迷わずリーチ。
たぶん、東出くんだって、他のメンバーだってそうする。
いまの例えはちょっと極端だったから、もしかしたらあかねちゃんもリーチしてるかもしれないけど、
まぁ、そういうこと」
話の核心が見えてこない。リーチを打つ回数が少ない、ということだろうか。
「ウチのルールだと、一発や裏にご祝儀が付くから、
リーチが少ないと祝儀負けする、っていうのも当然あるんだけど、
なにより、愚形を信用しなさすぎ。
早々にペンチャンやカンチャンを払っているところも、よく見かけたしね」
ここまで言われるとぐうの音も出ない。
確かに、思い返してみれば、
愚形を良形になるまでヤミテンにしておこうと思っている内に他家からリーチが掛かり降りたところ、
押していれば和了っていた、なんてことも少なくなかった。
「先制打っちゃえば、親だってまっすぐ打ちづらいし、
相手からはそれが愚形が良形かなんてわからないんだから、バシバシリーチ打っちゃえばいいの」
と締めくくって、あおいはブレーキを踏んだ。
窓から見える光景は、あかねにとってまったく未開の地で、停車した車の扉をおっかなびっくり開く。
とたんに、焦がした肉とタレの匂いが鼻腔をくすぐった。
くぅ、と小さく腹の虫がなって、慌ててあかねはお腹を押さえて照れ笑い。
「いらっしゃい」
店内に入るとこれまたとてつもないにおい。
もはや暴力ともいえるほどの強烈な香りに、身震いすらしてしまいそうになる。
「丸川さん、来たよー」
「おう、あおいちゃんかい。そっちの子は?」
「な、中井あかねと言います。あおいさんの後輩です」
丸川、と呼ばれた男は、背の高い浅黒い肌の男で、年のころは筒井と同じくらいだろうか。
笑った時に欠けた前歯が見えて、強面ながら愛嬌がある。
「へぇ、どっちの?」
「筒井さんの方。席どこ? 奥?」
「てっきりアフターだと思ってカウンターで取っちまったよ。個室にするかい?」
「ううん。カウンターでいいよ」
あかねちゃんは? とあおいが視線を向けてくれるが、
あかねは焼いた肉が食えればなんでもいいので、小刻みに首を縦に振るばかり。
丸川の案内で少し奥まったカウンター席に通される。
椅子に座った目の前には七輪がひとりひとつずつ。
見上げれば、換気用の排煙口。
「あかねちゃん、嫌いなものとかある?」
「ないですないです!」
「よかった。ここね、タンがすごくおいしいのよ」
あおいの合図で丸川が差し出してくれた皿の上には、大振りのタンが四枚。
それが、ひとり一皿ずつ出てくる。なにもかも、あかねの想像していた「焼肉」と違った。
あかねの知る「焼肉」は、テーブル席に円形の炭火コンロがひとつ用意され、
肉を注文すると、大皿にロースやハラミの肉のバラエティが提供される、というものだ。
ちょっと不安になって、小声で耳打ちするように、
「あおいさんあおいさん、もしかしてここって、結構高いんじゃあ……」
「うーん……」
もったいぶるようにあおいは、顎先に指を当てて、
「どう思う?」
小悪魔っぽく微笑んだ。
これは絶対に高いやつだ!
ありがたく思うのと申し訳なく思うのと同時に、あかねは一生あおいについていこうと思った。
「丸川さんウーロン茶ひとつと、……あかねちゃんは? お酒飲める?」
「え、あ、はい。いただきます」
「生? チューハイ?」
「ビ、ビールを……」
つい勢いで返事をしてしまったが、
高級なお肉をごちそうになってその上お酒までごちそうになっては、やはり申し訳なさが先立つ。
さっきまで自己主張の激しかった腹の虫も、なんだか少し引っ込み思案だ。
「はいよ、生とウーロン茶お待ち。あかねちゃん、だっけ? ジャンジャン食いなよ」
「いや、でも、その、私」
「気にしない気にしない。
今日は私が無理矢理連れてきたようなものなんだから、遠慮しなくていいの。
ほら、網もあったまってきたわよ」
するりとあおいの箸が伸びてきて、ぺとりと七輪の上にタンが落ちる。
(い、いいにおい……)
しかし腹具合というのはいつでも正直で、
脂の滴る様子、その脂に引火した炎が肉をあぶる匂いに、
すぐさまよだれが止まらなくなる。
「い、いただきます」
それからあかねは、無心になって、肉を口へ運んでいく。
タン、タン、ビール、ビール、ナムル、タン、ビール、
追加で出てきたロース、ビール、ロース、ロース、キムチ、
そしてとどめとばかりにカルビ、カルビ、ビール、ビール、カルビ。
あかねが正気に戻ったのは、五杯目のビールを空にして、ひと段落つき、
ふと、肉の焼ける匂いのほかに、かぎなれたにおいを感じた時だった。
「あれ、あおいさん」
隣を振り向けば、あおいが紫煙をくゆらせながら、微笑んでいる。
「煙草、吸ってたんですか?」
煙をひと吸い、そして吐き出す仕草が、唇がなまめかしい。
「うん、まぁね」
「でも、お店じゃ」
「ゴールデンタイムじゃ吸ってないキャラでいってるからね。
たぶん、いまのゴールデンタイムで知ってる人は、筒井さんと東出くんくらいじゃないかしら。
ほら、やっぱり煙草を吸う女って、ウケが悪いじゃない。だから内緒ね」
煙草の火をにじり消し、ウーロン茶を一口。
「引いた?」
「そんなことないです。でも、あおいさんって、不思議な人だなぁ、って」
あおいは、訝しそうに顔を歪めて、
「どういうこと?」
「えっと、あおいさんって、店でのシフト週三じゃないですか。
ほかの日は何をしてるのかな、って。
ほら、今日も、結構夜遅くに来てたりしたじゃないですか。
それに、週三シフトじゃ食べていけるような給料じゃないですし」
なるほど、ともっともらしく頷いて、
あおいはも一度グラスに口をつけ、頬杖を突いて、蠱惑的な流し目であかねを見つめながら、
「あかねちゃんは、どう思う?」
あかねは言葉に詰まった。彼女のその妖艶さもあるが
、聞いてはいけない、踏み入ってはいけない領域に、立ち入ってしまったような気がして。
「あの、その、私は……」
しどろもどろになってのけ反るあかね。
あおいの瞳は、挑発的に、目を逸らさない。
と、不意に、
「ぷっ」
そのあおいの唇が、歪に吊り上がった。
「あはははは! もう、そんなに真に受けないでよ」
今までの嫣然な笑みとは打って変わって、
手を叩いて大はしゃぎする子供のように大口を開けて笑うあおい。
「あおいちゃん、ちょっと脅かしすぎじゃないかい。
ただのキャバ嬢を、そんなにもったいぶらなくってもいいだろ」
あかねはあっけにとられて、思考が追い付かない。
頭の上に疑問符を並べて、辛うじて口にできた言葉は、
「キャバ嬢?」







