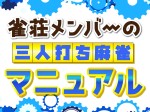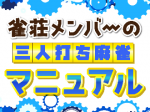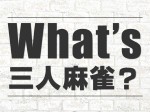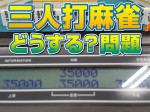ヤミテンを使いこなそう
ヤミテンとは、役アリ聴牌をリーチせずに和了すること、
もしくはその状態にしていることを言うが、
打点とご祝儀の関係から、リーチをかけて和了すること基本的な三人打ちにおいて、
しかしヤミテンは非常に重要な技術・戦略だ。
というのも、何度も言うようだが、三人打ちは四人打ちよりも、点棒をより意識してプレイするゲーム性であり、
ちょっとした放銃が、復帰不能な失点だったり、ドボンさえありうるからだ。
ゆえにヤミテンの基本的な使用方針は、親との対決を避ける、というものになる。
以下に、効果的なヤミテンの活用タイミングを、まとめていきたいと思う。
子で愚形先制聴牌
自分が子で、先制聴牌を入れたが愚形、という場合は、多くのケースでヤミテンにしておいた方がいい。
というのも、仮にリーチとしてしてしまって、親リーに追いかけられたひとたまりもないからだ。
むろん、和了のチャンスは減ってしまうが、
親リーに対してカンチャン/ペンチャンで対決してしまう、という愚を犯してしまうよりかは、はるかにマシだ。
ただし、愚形でリーチを敢行するのもやむなし、という場面も存在する。
それは、オーラス、親とトップ争いをしているような状況だ。
事ここに至っては、親への放銃やドボンなど、後のことを気にする必要はない。
放銃しようがツモられようが、結局はトップを逃してしまうのだから、
自身の和了を最優先に考えればいい。
親リーがかかっている中、聴牌した
親に先制リーチを打たれた最中、安牌を切っている内に聴牌が入る、ということも、往々にしてあるが、
多くの場合、ヤミテンに構えておく方がいいだろう。
特に役アリならば、愚形だろうが良形だろうが、ヤミテンが無難だ。
もしも、ここで親リーに対して追っかけリーチをした場合に考えられる状況はふたつ。
・もうひとりの子がオリて、親と直接対決
・もうひとりの子も参加しての殴り合い
ほとんどの場合は、前者のパターンで、親との直接対決を強いられることとなる。
親との1:1の対決は非常にリスキーな勝負で、オーラス和了トップ条件でもない限り、
できるだけ避けるべき状況だ。
かといって、後者のパターンもなかなか恐るべき状況で、
二軒リーチに対して、それでもなお突っ張ってくるということは、
自分の手牌に相当の自信があるということに違いない。
良形+打点十分で、親との直接対決するにも十分つり合いがとれている。
いくら相手が子といえど、そんな相手とも対決せねばならない、というのは、親リーもあいまって過酷な勝負だ。
しかし一方で、自分の手が親と勝負するにも十分というものなら、
親リーに立ち向かってもいいだろう。
子のリーチがかかっている中、聴牌した
子に先制リーチを打たれ、次巡に好形聴牌が入った。
さて、この時にリーチを打つべきかヤミテンにするべきか。
もちろん、追っかけリーチをかけて、親にプレッシャーをかけつつ積極的に和了を目指すのもよいが、
一方で、もっと防御的に、ヤミテンにして、
親リーがかかったらすぐにオリられるようにするのも悪くない。
いかなる点棒状況においても、親リーに放銃することは常に避けなければならず、
それはごく限られた条件を除いて、積極的に和了することよりも優先すべきだ。
愚形聴牌ならば、役アリであれ役ナシであれ、ヤミテンにしておく方が無難だろう。
子相手とはいえ、愚形で追っかけリーチを打つのは、やはり分が悪い。
南入以降、子で先制聴牌
南入以降は、ゲームメイク、ゲーム進行に特に神経を使っていかなければならない局面が続く。
オーラスに向けて、トップが取れるように点棒を調整する必要がある。
例えば南二局:西家で、暫定トップという点棒状況ならば、
配牌を開くまでに、するべきことがほぼ決定している。
それは、いかに「局を消化するか」ということだ。
南二局で親に連荘されて、トップ争いから脱落する、ということも珍しくない。
だから、点棒優勢で迎えた南場は、速やかに局の消化に努めるべきだ。
特に親番がもう残っていないとなれば、大きな失点を取り戻すことが不可能で、
なおさら局の消化に尽力するべきだろう。
例えば、平和ドラ4を聴牌したとして、リーチをかければ跳満確定ではあるが、
当然のヤミテン選択だ。
リーチをかけて、他家にプレッシャーを与えて進行を阻害する、というのはあまり得策ではない。
なぜなら、それは和了率を下げるだけのリーチでしかなく、
そのせいでもうひとりの子にベタオリでもされたなら、出和了の確率は一気に半減となるからだ。
突き詰めてしまえば、点棒優勢状況下では、自分が和了る必要すらないと言える。
親にさえ連荘されなければ、もうひとりの子が和了ることで、局は進むのだ。
先制聴牌したが、打点が低い
例えば東三局:南家、七巡目。おそらく先制で、タンヤオドラ1を好形で聴牌した。
が、局面を見渡してみると、親が華を3枚抜いている。
こんな場面で、聴牌したから即リーチ、というのは、かなり危険だ。
自分にドラがない時は、他家にドラが多く集まっていると考えるべきで、
(実際は、山にたくさん埋もれていることも多いのだが)
いかに好形リーチといえど、子に追いかけられた時すら、
打点面でつり合いが取れず、不利な勝負を迫られるおそれがある。
そしてこれが仮に役ナシドラ1の手であっても、場合によってはヤミテンを推奨したいケースもある。
役ナシドラ1をリーチするということは、親に追っかけられた際に、
リーチドラ1の安手で、親に全ツッパしているのと同じことだ。
リーチをかける時は、十分に勝負になる打点と待ちで臨むことにしよう。
先制聴牌したが、親/子の打点が高そう
これはほぼ同じような理屈なのだが、
例えば東二局:西家、11巡目。おそらく先制で、タンオヤ平和ドラ4で聴牌したとする。
一方で、親は河を見る限り、筒子の清一色/混一色を目指しているようだ。
こんな場況で聴牌即リー、というのもやはり危うい。
親がイーシャンテンなら、リーチなどなにも気にせず押してくるだろうし、
もうひとりの子にオリられ、親と一騎打ちとなってしまうのも、具合が悪い。
リーチをかけて倍満を目指したところではあるが、そこをぐっと堪えて、
ヤミテンに構えて少しでも和了確率を上げる方がいいだろう。
TIPS:判断の分かれるヤミテン
ここから先は、プレイヤーによって非常に判断の別れる部分で、
むしろヤミテンよりもリーチした方がいい、という人もいるだろう。
あくまで、ひとつの参考意見として読んでいただけると幸いだ。
親番でのヤミテン
三人打ちにおける親番は、いわば大量得点チャンスで、
ほとんどの場合、ヤミテンにすることはないだろう。
たとえ愚形であっても、先制であればリーチを打って、他家への押さえつけを図るべきだ。
しかし次に紹介するのは、親番で使うヤミテンの一例だ。
南一局:東家で、持ち点が60000点程度だったとする。
そして、子ふたりの点棒が20000点程度で、並んでいるとする。
この点棒状況において、好形でタンヤオドラ3を聴牌した場合、
多くのプレイヤーがリーチをかけて、跳満を目指すだろう。
しかし、ここであえて満貫止まりのヤミテンを仕掛けることで、以下のような効果が見込める。
- 和了率がぐっと上がる
- 片方の子がドボン寸前となり、もう片方の子がトップよりもトビ賞を狙いに行く
- 以降、他家があなたに対して、ヤミテンを警戒するようになる
リーチよりもヤミテンの方は、和了率が上がるのは言わずもがなだが、親番の場合は特に顕著だ。
三人打ちは親番で点数を稼ぐゲームなのだから、よもやヤミテンなどしてくるまい、という考えがあるからだ。
そして、どちらか片方の点棒を出和了で大きく削ることにより、そのプレイヤーのみならず、
もうひとりの子に対しても、トップを困難にすることができる。
というのも、一方の点棒がドボン寸前になってしまったことにより、暫定トップのプレイヤーをまくるよりも先に、
そのプレイヤーがトンでしまう、という事態になりかねないのだ。
最後に、思いがけないヤミテンに突き刺さることで、放銃してしまったプレイヤーは、
それ以降あなたに対する警戒度をぐっと引き上げる。
中盤に中張牌を二、三枚切り出しただけで、「もうヤミテンしているのではないか?」という疑念を持たせることができるのだ。
オーラス、点棒圧倒時のヤミテン
オーラス:西家で、点棒が60000点近く持っていたとして、
序盤に役ナシ両面聴牌が入った。
素直にリーチと宣言して、和了ってフィニッシュ、というのももちろん悪くないが、
ヤミテンという選択肢も頭に入れておくと、戦術の幅が広がるだろう。
この局面でヤミテンをするメリットはふたつ。
ひとつは当然、親への打ち込みを回避できること。
そしてもうひとつは、子への打ち込みができることだ。
親に跳満や満貫をツモられれば逆転されるが、子に対してならば、三倍満でも放銃しない限り、トップが取れる、
というような点棒状況は、三人打ちにおいてはわりとよく見られるもので、
むろん自分で和了することでトップを取りに行くのも正しいが、
どうしても和了が厳しい、というような場面では、子への打ち込みも積極的に狙っていこう。