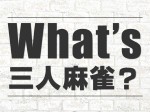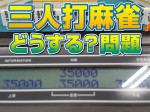■三人打ちと混一色
混一色とは、字牌といずれか一種類の数牌からなる手役のことで、
門前3翻、食い下がり2翻。
四人打ちでも、手軽に打点を狙えることから、
配牌を開いた時に、容易に門前でまとまりそうにない時などに、
他家のプレッシャーがてらに色を寄せていくプレイヤーは多い。
手牌の色を一色に絞ることにより、
上家の手牌は自由な打牌に制限がかかり、
特にその相手が親の場合、好結果を残すことも少なくない。
では、三人打ちにおいて混一色は、どのような立ち位置にあるだろうか。
三人打ちでは、萬子の二~八が除かれていることから、
混一色を作るのは、至極容易だ。
混一色は門前で3翻と強力な手役で、役牌やドラと絡めて、
倍満・三倍満が清一色に続いて狙いやすい。
また、鳴いても2翻あり、
その上他家が不要としやすい字牌に照準を合わせることができるため、
使い勝手の良さとしても評価が高い。
ただし、もちろん問題点もいくつか存在する。
〇混一色の弱点
数牌の種類が一種類しかないため、
残るもう片方の数牌の受けを完全にシャットアウトしてしまう訳で、
手牌進行が著しく遅くなってしまう場合もある。
そうこうしている内に先制リーチを受けて、
完全にベタオリするほかない、ということもしばしば。
また、鳴いて2翻といっても、
それはリーチをかけてツモるのと同様の打点であり、
さらに裏ドラの乗りやすい三人打ちでは、
鳴いて混一色するくらいなら、手なりでリーチをかけてツモ和了した方が、
高打点のこともある。
それから、全赤華アリルールを採用している時に、
特に顕著な弱点であるが、
色を絞るということは、
もう片方の色の赤ドラは使うことができず、
しかも、表ドラまでそっちの色だったなら、
合計8枚ものドラを無駄に河に流さざるを得ない。
最後に、上記の理由から、
完成形の打点がそれほど高くないことが、
他家にも察知されてしまうことがあり、
その場合には、せっかくのプレッシャー効果が弱まり、
特に親相手にガンガン突っ込まれて、押し切られてしまいがちだ。
〇混一色と配牌
四人打ちにおいて混一色へ向かうには、
配牌から狙いを澄ましておくことが多い。
むろん、三人打ちにおいても、
少なからずそういうもので、(むろん、途中から移行することも多いが)
では、どのような配牌をもらった時に、混一色を目指すのがよいだろうか。
例1)
例2)![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
例3)![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
こういう手牌で、特に点棒に余裕のある親番の時、
筆者は混一色を目指すことが多い。
挙げた3例はいずれもマージナルな配牌で、
反対意見の多いことも承知の上で申し上げるのだが、
少なくとも、筆者は混一色を狙う価値は小さくないと思っている。
もちろん、カンチャン・ペンチャン搭子を大事するのも、
悪手だとは思わないし、
これがもしも、両面ターツなら、
手なりで進める方が多くの場合正着となりうるだろう。
特に、例1、2は小車輪を目指しながら、
最悪、必要に応じて門前を崩したとしても、
跳満まで見据えることができるだろうし、
例3は、ふつうに七対子をにらみつつ、
どこかで⑥⑥を払ってもいいだろう。
※1、2、3、いずれも門前で手牌進行することを前提としており、
愚形の残る牌姿で仕掛けることは、手痛い反撃を受けることが少なくない。
詳しくは、「三人打ちと仕掛け」を参照。
②配牌でいずれか一色の二面子+アルファが完成している。もしくはそれに準ずる形
例4)![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
例5)![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
例6)![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
例4はわかりやすく、
これをわざわざ索子面子を伸ばしていこうとする人は少ないと思う。
字牌を重ねて、混一色を見るだろうし、
5の周りが引っ付いてターツになれば、
それを重用してリーチといくのも十分有効だ。
例5は微妙で、配牌2シャンテンということを考慮すると、
第一打![]() というのがマジョリティと思うが、
というのがマジョリティと思うが、
索子を捌いて、筒子を集めていく攻め方もなくはない。
そして例6だが、これを混一色と見るのは、
すこし無理がある。
索子搭子が非常に使い勝手がよく、
筒子部分がやや悪形で、筒子と字牌だけで面子を構成するのは難しそうだ。
〇混一色と鳴き判断
混一色は手軽に、
倍満・三倍満を狙いにいける役といったが、
やはりあくまでそれは、
門前でリーチまで辿り着いた時であることがほとんだ。
だからといって、毎度毎度、
門前だけで進められるかといえば、そういう訳でもなく、
字牌や数牌を叩かねばどうしようもないケースもあるのだから仕方がない。
では、どのような牌姿、タイミングで鳴くのがふさわしいか、
もしくは、スルーすべきかを、すこし考えてみたいと思う。
例7)![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
例8)![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
例9)![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
上に示したような牌姿でポンテンを取ってしまうのは、
基本的にナンセンスと言っていいだろう。
例7、8ですら満貫(12000)、
例9に至っては3翻止まりという、驚くべき安さだ。
例9のように鳴いて両面聴牌を取れる場合でも、
終盤局面でもない限り、取るべきではない。
それならば、両面を入れて、
シャンポン待ちリーチでもする方が、いくらかマシだ。
残りツモ数が3~4枚しかないような、終盤でもない限り、
鳴いてせいぜい満貫という聴牌は、あまりありがたくない。
仮に、河に出てきた字牌が最後のものであっても、
序盤であれば飛びつかず、字牌対子を払って清一色を目指した方が、
他家も動きづらくなるだろう。
ただし、鳴いて跳満あるのであれば、よほどの序盤でもない限り、
素直にポンテンを取るのが無難だろう。
②自分が子。1シャンテンの状態で、ポンテンの字牌・数牌が出た (ドラはもう一方の色とする)
例10)![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
例11)![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
例12)![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
①とまったく同じ牌姿を例として用意したが、
親と子ではちと事情が異なる。
いずれもよほどの序盤でない限り、
ほとんどの場合聴牌をとって構わないだろう。
せっかくの混一色なのだから、打点を重視する、
というのももちろんひとつの考えだが、
中盤に差し掛かると、
やはり親からの攻勢がいよいよ恐ろしくなってくる。
親が仕掛けて、しかも安そうならば門前進行も問題ないが、
それ以外の場合は、
ポンテンをとっていつでも和了れる体勢をとっておくにこしたことはない。
例12のような両面聴牌なら、安かろうと価値があるし、
例10、11のような愚形でも、好形への変化も十分だ。
③親、子不問。一色+字牌で、4対子ある状態で、鳴くことのできる数牌・字牌が出た。
例13)![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
例14)![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
混一色を目指していて、よく出遭うのが、上のような牌姿だ。
面子手で見れば3シャンテン、
七対子で見れば2シャンテンという、微妙な牌姿の時、
上家が切った牌に思わずコシってしまう経験も、少なくないだろう。
むろん、他家の進行具合や点棒状況によりケースバイケースなのだが、
基本的には鳴かない方が安全運転といえるだろう。
門前でも小車輪聴牌が目指せるのだから、
無理して鳴いて、挙句愚形聴牌というのは、
やはりすこし興ざめだ。
カンチャンやペンチャンが埋まり、字牌を払っての好形リーチというのも、見えなくはない。
〇混一色とオリ判断
初心者に多いケースではあるが、
混一色を聴牌しているから、あるいは1シャンテンだからといって、
オリた方がよい局面で、手牌に引きずられて、
むざむざ点棒を放出していることをよく目撃する。
ひとつは、混一色に対する評価が正しくできていないことに、
起因していると考える。
本項にて、
混一色の威力、使い勝手、魅力、評価など、さまざま書いたが、
所詮は2、3翻役だということを頭に置いておかなければならない。
それはすなわち、メンピンやメンタンピンと同じ価値であり、
子のリーチと五分、親のリーチとは常に分が悪いのだ。